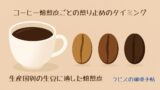ネット上には、多くのコーヒー生豆の販売サイトがあって、その多くは小分けにも応じてくれます。
コーヒー生豆は、焙煎された豆よりもかなり安く入手できますし、なにより自分で焙煎すれば、いつでも焙煎したてのコーヒーを手軽に楽しむことができます。
本記事では、コーヒーを飲みたい時に、飲みたい量を、自宅で簡単に、焙煎する方法を紹介します。
これから、コーヒーの焙煎に挑戦してみたいという方の参考になれば幸いです。
焙煎の本質
コーヒーは生豆の状態では青臭いだけで、味も香りもありませんが、加熱することにより、化学変化を起こさせることで、コーヒー独特の味や香りが引き出されます。
つまり、コーヒー焙煎の本質は「化学変化」だといえます。
焙煎時の熱の加え方や加熱時間によって、引き出される風味が変わるため、コーヒーの香りや味わいは焙煎に大きく左右されます。
生豆には、10~13%程度の水分が含まれていますが、焙煎の初期の段階(業界用語で「蒸らし」又は「水抜き」という)でその水分が抜けていきます。
水分が抜ける(豆の色が、肌色になる)までは、豆の表面だけが焼けてしまう生焼け(芯残り)にしないために、中火以下で焙煎します。
そこからの火のかけ方(温度の上げ方や下げ方)と煎り止めまでの時間のかけ方が、コーヒーの風味を決定づける重要なポイントになります。
少量の焙煎に使用する器具の選択
少量の生豆を焙煎する場合は、その焙煎する量に応じて、使用する器具を使い分けています。
焙煎する量は、毎回一定にした方が、焙煎後の検証もしやすく、コツをつかみやすいと思います。
ゴマ煎り器と焙烙
50gくらいまでは、使用する器具として「ゴマ煎り器」や「焙烙(ほうろく)」を使います。

ゴマ煎り器
画像は、直径約12cm、深さ約2cmのゴマ煎り器ですが、少量のコーヒー生豆を焙煎することもできます。

焙烙(ほうろく)
主に豆、ゴマ、茶葉などを炒るための厚手の素焼きの土鍋ですが、コーヒー生豆を焙煎することもできます。
30g~50gくらいの少量を焙煎するコツ


1.火力に注意して、生焼けにならないようにする。
…焙煎する量が少ないので、温度の上昇が速く、焙煎時間も短くなってしまい、強火で焙煎すると、豆の表面だけが焼けてしまう生焼け(芯残り)しやすくなりますので、適宜火力を調節して、生焼けにならないように注意します。
2.煎りムラが出ないように、たえず煎り器を振り続ける。
…煎り器を振るときは、炎の中心から大きく外れないようコンパクトに、煎りムラが出ないように、たえず煎り器を振り続ける必要があります。
…たえず振り続ける必要があるため、火力は「中火」くらいに固定しておいて、途中で細かく調節せずに、炎からの距離(振る高さ)で調節するようにします。
手鍋
200gくらいまでは、使用する器具として「手鍋」を使います。
手鍋のサイズは、150gくらいまでは直径14cmのものを、200gくらいまでは直径16cmのものを、焙煎する量に応じて、使い分けています。
生豆の量が200gより多くなると、煙やチャフの量が多くなるので、お勧めしません。

手鍋
鍋の材質は、アルミ製のものを使っています。
ステンレス製のものもありますが、アルミはステンレスと比べて、熱伝導率が非常に高く、熱を素早く伝える性質があります。

手鍋のフタ
鍋のフタには、煙がこもらないように、小さな穴のあいたものを使います。
個人的には、100gから150gくらいの生豆を、手鍋を使って焙煎することをおすすめします。
コツをつかめば、本格的な焙煎機にも負けない、おいしいコーヒーを焙煎することができます。
なぜ「手網」ではなく「手鍋」が適しているのか?
1.たえず振り続ける必要がない。
…たえず振り続ける必要がないので、腕が疲れない。
…たえず振り続ける必要がないので、豆の様子を、よく観察できる。
2.手鍋はフタを開け閉めすることができる。
…手鍋はフタを閉じられるので、気密性が高く、手網ほどチャフが飛び散りにくい。
…対流熱を活かせるため、手網と比べて、ムラなく焙煎しやすい。
…フタを開閉することによって、排気の調整ができる。
手鍋焙煎に必要な道具類
◎注意事項 … 実際に焙煎をする際には、やけどを防止するため、軍手などを着用し、特に深煎りの場合は、相当量の煙が出ますので、換気することを忘れないようにしましょう。
1.片手鍋
2.カセットガスコンロ
3.キッチンタイマー
4.金属製のザル(焙煎した豆の冷却に使います)
5.うちわ(焙煎した豆の冷却に使います)
6.生豆


生豆について個人的には、コロンビア産のものが、粒がそろっており、均一に火が通るので、初心者にはおすすめです。反対に、欠点豆が多く、水分値にバラつきの多いマンデリンは、焙煎が難しく、初心者にはおすすめできません。
手鍋によるコーヒー焙煎の流れ
手鍋によるコーヒー焙煎のおおまかな流れをまとめてみました。参考までに、目標とする焙煎時間の目安も表示しています。
この時間と豆の状態を目安として、例えば「7分くらいで豆が黄色っぽくなるように、10分くらいで1ハゼがくるように」と火力を調節しながら焙煎するようにします。
また、焙煎時の火力は、その日の気温や湿度、投入する生豆の量などの前提条件の違いによっても、調節が必要になってきます。
最初から思うようには行きませんが、トライ&エラーを繰り返すうちに、徐々にコツをつかんで、うまく狙いどおりに焙煎できるようになってきます。
なお、時間や火力についての表示は、ケース by ケースですので、数値はあくまで一つの目安として参考にしてください。
| 時間の目安 | 焙煎のおおまかな流れ | 火力の目安 | 煎り止め |
|---|---|---|---|
| (30秒~1分) | 予熱 | ||
| 0 | 生豆の投入 | 弱めの中火 | |
| 3分 | ボトム(ターニングポイント) | ↑ 中火 | |
| 5分 | (豆が肌色になる) | ||
| 7分 | (豆が黄色っぽくなる) | ↑ 強めの中火 | |
| 10分 | 1ハゼ(パチパチ) | ↓ 弱めの中火 | |
| 11分30秒~40秒 | (1ハゼの終わり) | ↑ 中火 | ⇒ ミディアム |
| 12分~12分30秒 | (1ハゼの終わりと2ハゼの中間) | ⇒ ハイ | |
| 13分30秒 | 2ハゼ(ピチピチ) | ↓ 弱めの中火 | ⇒ シティ |
| 14分~14分10秒 | (2ハゼのピーク手前) | ↓ 弱火 | ⇒ フルシティ |
| 2ハゼのピーク | |||
| 14分40秒~50秒 | (2ハゼの終わりまでの間) | ⇒ フレンチ | |
| 2ハゼの終わり | |||
| 消火 | |||
| 煎り止め |
手鍋焙煎のやり方(要点)
手鍋によるコーヒー焙煎のポイントを、時系列に沿ってまとめてみました。
1.焙煎前のハンドピックをします。
…色の黒い豆や白い豆など他の豆に比べて極端に色の違う豆、欠けたり割れている豆、貝殻のようになっている豆、小さい穴の空いた虫食い豆、石や木くずなどの異物などを焙煎前に取り除きます。
2.鍋を予熱した後、生豆を投入します。
…予熱は中火で、30秒~1分の範囲内で、その日の室温などによって適宜、時間を調節します。
3.フタをした鍋を、前後に水平に、ゆっくり大きめに、ゆすって豆を撹拌します。
…「4~5秒ゆすったら、4~5秒コンロの火にかける」を繰り返します。
…フタが飛ぶと危険ですので、決して鍋をあおらないようにします。
4.3分経過 ⇒ フタの内側に水滴が付いてきます。
…フタの内側に水滴が付き、くもってきますが、まもなく消えていきます。
5.5分経過 ⇒ 豆が肌色になります。
…豆の色が、うす緑色から徐々に「肌色」になってきたら、水分が抜けてきた状態です。
…シルバースキンが薄皮(チャフ)となってはがれ、鍋のフタの内側に張り付き始めます。
6.豆が黄色っぽくなります。
…焙煎を進行させるため、このあたりで、すこし火力を強めます。
…この「豆が黄色っぽくなる」までの時間を、毎回合わせることで、手鍋による焙煎は安定してきますので、重要なチェックポイントです。
7.1ハゼがきます。
…焙煎は温度が高い時に大きく変化します。急激な温度の上昇を抑えるため、火力を落とします。
…時おりフタを開けて、煙を排出します。
…フタが飛ぶと危険ですので、フタはしっかり閉じるようにします。
…鍋をコンロに置く時間を短くします。「4~5秒ゆすったら、1~2秒コンロの火にかける」を繰り返します。
8.1ハゼが収まります。
…焙煎を進行させるため、すこし火力を強めて、徐々に温度を上昇させます。
…フタは開けずに閉めた状態で、焙煎を進めます。
…2ハゼが近づくにつれて、白い煙が多く出始めます。
9.2ハゼがきます。
…焙煎は温度が高い時に大きく変化します。急激な温度の上昇を抑えるため、火力を落とします。
…頻繫にフタを開けて、煙を排出します。
10.消火後、煎り込みをします。
…タイミングを見計らって消火したら、余熱を使って焙煎(煎り込み)を進めます。
…豆の状態をよく見て、煎り止めのタイミングをはかります。
11.煎り止めします。
…煎り止めのタイミングで豆をザルに出したら、うちわを使って速やかに冷却します。
12.焙煎後のハンドピックをします。
…焦げた豆や色の薄い豆は、味が悪くなるので取り除きます。
焙煎プロファイルを残しておく
コーヒー生豆は、農産物ですから、たとえ同じ農園で採れたものであっても 工業製品のように、まったく同じものには、なりえません。
それぞれの豆によって適切な焙煎度は異なるので、豆ごとに、そのポイントを見極めて煎り止めることが必要になります。
焙煎度ごとの煎り止めのタイミングについては、別の記事でも紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。↓こちらの記事
そして「毎回、目標とする風味に仕上げる焙煎技術」の習得が必要になります。
そのためには、目標とする焙煎プロファイル(コーヒー豆をどのように加熱して焙煎するかのレシピ)に基づいて「この豆は何分で1ハゼがくるように、何分で焙煎が終了するように」とロースター(焙煎する人)自身がよく考えて、火力などを調節するようにします。
また、次回以降の焙煎に活かすため、焙煎の記録を取っておくことも、とても大切になります。
次のような項目を記録に残しておくと、次回以降の焙煎の参考になります。
・ 焙煎日、天気、気温、湿度
・ 生豆の情報(産地・品名・精製方法など)
・ 投入生豆の重量と焙煎後の重量、歩留まり(生豆を焙煎した際の重量変化)
・ 焙煎時間(豆が黄色、1ハゼ、2ハゼ、消火、煎り止め)
・ 試飲(試飲日、抽出方法/香り、酸味、苦味、甘み、コク、後味、バランス、雑味や渋みなどの異味異臭、経時変化など)
効率的なコーヒー焙煎の習得方法
3ステップで、コーヒー焙煎をマスターするのが、効率的です。
1.シティローストをマスターする。
まずは、コーヒー生豆が、どのような経過をたどって、2回目のハゼに至るのか、その過程をよく観察します。
2.フレンチローストをマスターする。
次に、焙煎の進行が特に速くなる2ハゼ以降で、豆に油が浮いてくる状態を確認しつつ、深煎りの煎り止めのポイントを見極めます。
3.ミディアムローストをマスターする。
最後に、1ハゼの終わりから2ハゼに至るまでの、煎り止めのポイントを見極めます。
まとめ

コーヒー生豆は、焙煎された豆よりもかなり安く入手できますし、なにより自分で焙煎すれば、いつでも焙煎したてのコーヒーを手軽に楽しむことができます。
本記事では、コーヒーを飲みたい時に、飲みたい量を、自宅で簡単に焙煎する、ゴマ煎り器と焙烙を含むいくつかの方法を紹介しました。
コーヒーの焙煎にチャレンジしてみたいという方の参考となるように、手鍋による焙煎に必要な道具類から手鍋焙煎の流れ、やり方のポイントなども紹介しました。
手鍋を使っての焙煎はシンプルな料理を作る感じで、思っているより、簡単です。
ぜひ、気軽にチャレンジして、新しいコーヒーの世界に、足を一歩踏み入れてください。